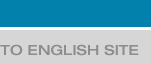応用編
模倣品を発見したら
特許・意匠・商標などで保護されている自分の商品とそっくりな商品が出回っていることを発見したら、まずは、弁理士に相談することをお勧めします。自分で対応しようとしたために、後々話がこじれ、無用な裁判に発展するケースもあるからです。
模倣品に対しては、まず、そのものを入手し、特許などの権利と抵触していることを確認し、必要に応じて、弁理士等の鑑定を依頼します。そして、侵害という結論に至った場合は、その侵害者に、警告書を送付し、侵害行為の中止を求めることが必要です。
また、仮に商標権などを有してなくても、自分の商品の商標や、その容器・包装あるいは商品の形態などが周知なものであれば、不正競争防止法により、その模倣行為をやめさせることができる場合もあります。
さらに、侵害品が輸入品の場合は、特許権・実用新案権、意匠権、商標権等に基づき、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続きを執るべきことを申し立てる輸入差止申立制度も有効です。
模倣品に対しては、まず、そのものを入手し、特許などの権利と抵触していることを確認し、必要に応じて、弁理士等の鑑定を依頼します。そして、侵害という結論に至った場合は、その侵害者に、警告書を送付し、侵害行為の中止を求めることが必要です。
また、仮に商標権などを有してなくても、自分の商品の商標や、その容器・包装あるいは商品の形態などが周知なものであれば、不正競争防止法により、その模倣行為をやめさせることができる場合もあります。
さらに、侵害品が輸入品の場合は、特許権・実用新案権、意匠権、商標権等に基づき、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続きを執るべきことを申し立てる輸入差止申立制度も有効です。
先使用権の証拠作成方法
特許法では、他人の特許にかかる発明を、独自開発により、他人の特許出願の際に現に実施していたり、実施の準備をしていた者に対して、先使用権が認められ、その者の特許発明の実施は特許権を侵害しないとされます。
それでは、この先使用権が認められるためには、具体的に、どのような方法で発明実施やその準備をしていたことを立証したらよいのでしょうか。
有効な手段として、公証人に「事実実験公正証書」を作成してもらったり、私署証書に確定日付を付与してもらう方法があります。ここで、「事実実験公正証書」とは、公証人が聴取した陳述、目撃した状況等を録取して、かつ実験方法を記載して作成されるものです。この方法によれば、公正証書に録取された事実が、作成時に確かに存在したことを立証する書証となります。また、後者の方法では、作成年月日・作成名義人の署名又は記名押印のあるものに確定日付を付与してもらい、確定日付の当日に、その文書が確かに存在していたことを立証することができます。
このような方法で作成した証拠と、自社で保管している他の証拠を組み合わせることにより、先使用権の存在を主張、立証できます。
それでは、この先使用権が認められるためには、具体的に、どのような方法で発明実施やその準備をしていたことを立証したらよいのでしょうか。
有効な手段として、公証人に「事実実験公正証書」を作成してもらったり、私署証書に確定日付を付与してもらう方法があります。ここで、「事実実験公正証書」とは、公証人が聴取した陳述、目撃した状況等を録取して、かつ実験方法を記載して作成されるものです。この方法によれば、公正証書に録取された事実が、作成時に確かに存在したことを立証する書証となります。また、後者の方法では、作成年月日・作成名義人の署名又は記名押印のあるものに確定日付を付与してもらい、確定日付の当日に、その文書が確かに存在していたことを立証することができます。
このような方法で作成した証拠と、自社で保管している他の証拠を組み合わせることにより、先使用権の存在を主張、立証できます。